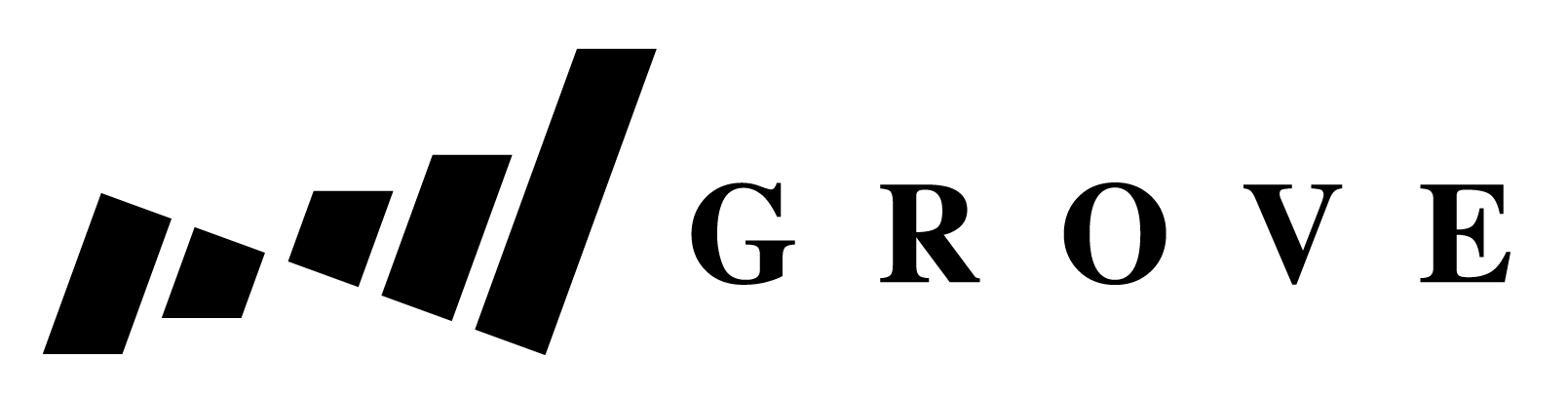なぜスタートアップの税理士選びは難しいのか。
多くのスタートアップ創業者が税理士選びに苦心する背景には、一般的な税務サービスとスタートアップ特有のニーズとのミスマッチが存在します。
従来の税理士サービスは既存企業(一般的なスモールビジネス)向けに最適化されており、急速な成長や柔軟な事業展開を特徴とするスタートアップの要件に必ずしも適合しないケースが少なくありません。
スタートアップの税理士選びが特に難しい理由は、主に3つの要因に集約されます。
第一に、通常の税理士とスタートアップに特化した税理士の違いが外見からは判別しづらいという点です。多くの税理士事務所がウェブサイトでスタートアップ支援を謳っていますが、実際の支援実績や知見には大きな差があります。
第二に、スタートアップ特有の課題に対応できる税理士が依然として少ないという現実があります。特に、シード期からアーリー期における収支計画、資金調達、バックオフィス体制の構築など、スタートアップ特有の専門知識が必要な場面で、適切なアドバイスができる税理士は限られています。資金調達についても、デット(借入)の知見はある税理士は多い一方で、スタートアップの主流となるエクイティでの調達になると、知見のある税理士はほとんどいません。希少であるという事は、当然探すのが難しいということに繋がります。
第三に、税理士または税理士事務所との相性が合うとは限らない、ということです。創業初期の段階において税理士がスタートアップアドバイザーとして貢献できる余地は非常に大きいです。つまり、会社の経営に深く関わってくる存在なので、創業者との相性が良くないとコミュニケーションにすれ違いが生まれ、適切なシナジーが生まれません。スタートアップアドバイザーとしてのスキルは要件を満たしていても、創業者との相性でミスマッチとなる可能性も大いにあるということです。
この記事では、スタートアップ創業者がどのような観点で税理士を選ぶべきか、について解説していきます。
スタートアップに最適な税理士の要件とは?
スタートアップに最適な税理士は、以下の3つの核となる能力を備えていることが重要です。
第一に、スタートアップの成長ステージに応じた支援力です。創業期特有の経理体制構築から、資金調達を見据えた帳簿管理、さらにはスケーラブルな経理システムの設計まで、包括的なサポートが求められます。例えば、シードファイナンスにおいてどのようなVCからどのような条件で資金調達をすべきか、融資は検討すべきか、などスタートアップのステージと状況に応じた適切なアドバイザリーを提供できるかどうかは重要なポイントです。
第二に、迅速かつ柔軟な対応力が不可欠です。スタートアップの事業環境は急速に変化するため、従来の税理士サービスにおける定型的な対応では不十分です。オンラインでのコミュニケーションツールの活用や、急な相談への即応体制など、柔軟な対応力が重要となります。slackやChatworkでの連絡や、googleDriveでのファイル共有ができるという最低限のリテラシーは当たり前に備えている必要があります。
第三に、経営者目線でのアドバイス力です。税務面のサポートにとどまらず、資金繰りや事業戦略に関する実践的なアドバイスを提供できる能力が求められます。ビジネスサイドにおける経営知見を持った税理士は希少で、さらにスタートアップビジネスを理解している税理士は全国を探しても数えるほどしかいないでしょう、特に、資金調達や組織拡大期における経営判断において、税務の専門家としての知見を活かした助言は非常に価値があります。
参考:シードステージのスタートアップ企業が提携すべき税理士の特徴どのように選べばいいのか?
適切な税理士の選定には、体系的なアプローチが必要です。
まず、情報収集の段階では、スタートアップ専門メディアや創業支援機関、先輩起業家からの紹介など、複数のチャネルを活用することが重要です。特に、スタートアップ支援の実績を持つ税理士の情報は、同じ経路で事業を展開している他の創業者からの紹介も有効です。
初期スクリーニングでは、各税理士事務所のホームページや提供サービスの内容を詳細に確認します。特に注目すべき点として、スタートアップ支援の具体的な実績、コミュニケーション方式の柔軟性、料金体系の透明性が挙げられます。
この段階で、自社のニーズと明らかにマッチしない候補を除外することで、効率的な選定プロセスを進めることができます。
面談段階での確認ポイント
候補となる税理士との面談では、以下の観点から詳細な確認を行うことが重要です。
まず、スタートアップビジネスに対する理解度です。一般的な税務知識だけでなく、スタートアップ特有の課題や成長過程における重要なポイントについての知見を確認します。スタートアップは、既存のビジネスを新たに始めるスモールビジネスと違い、新たなビジネスモデルやイノベーションによってこれまでになかったビジネスを生み出すものなので、旧来型の常識でアドバイスをするとむしろ悪い方向に導いてしまう可能性すらあります。PMFやJ-KISS、バーンレート、ランウェイなどスタートアップでは頻出の用語についても理解できていることは必須となります。
次に、コミュニケーションの相性です。特に、主担当者となる税理士との対話の質は、長期的なパートナーシップにおいて極めて重要です。質問への応答の明確さ、説明の分かりやすさ、問題解決へのアプローチ方法などを評価します。
さらに、提供サービスの具体的な内容と範囲について、詳細な確認が必要です。月次の税務業務に加え、経営相談や資金調達支援などの付加価値サービスの有無、それらに対する料金体系を明確にしておくことが重要です。
創業初期において、スタートアップはバックオフィス要員を雇用するほどのリソースはありません。しかし、コアメンバーがバックオフィス業務にリソースを取られてしまうことは、事業の加速に悪い影響を与えかねません。税理士事務所がバックオフィス業務も受けられるのか、は必ず確認するようにしましょう。
費用相場、料金感について
税理士に対する報酬は、安ければ安いほど良いと思われがちですが、それは大きな間違いです。とにかく税務申告の作業だけをお願いしたい、という場合にはそれほど金額にこだわる必要はないかもしれませんが、しっかりとスタートアップの知見を持った税理士に依頼する場合はそれなりの相場観を持っておいた方が良いでしょう。
具体的に言えば、創業初期においても年間60万円~100万円程度(顧問料と決算料込み)の金額感は持っておいた方が良いでしょう。例えば年間30万円程度の税理士の場合、ほとんどサポートが受けられずただの税務の外注先となってしまう恐れがあります。
とにかくコスパを求めて安い税理士に頼んだ結果、ろくなサービスを受けられず結果的に顧客満足度が低いというケースは往々にしてあります。リソースのない創業初期は、キャッシュ不足に陥る懸念から安い税理士に頼んでしまいがちですが、事業運営にかなり深く関わる経営判断のためしっかりと考えましょう。
契約時の留意事項
税理士との契約締結に際しては、将来を見据えた包括的な合意形成が重要です。基本的な税務サービスの範囲に加え、以下の点について明確な取り決めを行うことを推奨します。
まず、契約条件の詳細です。最低契約期間の有無、中途解約時の条件、業務引継ぎの範囲などについて、具体的な合意を形成します。特に、スタートアップの事業環境は急速に変化する可能性があるため、柔軟な契約変更や解約条件を確保しておくことが望ましいでしょう。
次に、将来の成長に対する対応方針です。組織規模の拡大や事業領域の変更に伴うサービス内容の変更、それに応じた料金改定の基準などについて、予め合意しておくことで、円滑な関係維持が可能となります。
パートナーシップの構築に向けて
適切な税理士とのパートナーシップは、スタートアップの持続的な成長を支える重要な基盤となります。選定プロセスにおいては、単なる費用比較や表面的な実績確認にとどまらず、自社の成長戦略との整合性や、長期的な協力関係の構築可能性を重視することが重要です。
特に注目すべき点として、税理士の専門性や対応力に加え、スタートアップの価値観や事業目標への理解度が挙げられます。相互理解に基づく信頼関係の構築が、効果的なパートナーシップの基盤となるためです。
また、定期的なコミュニケーションを通じて、サービス内容や支援体制の最適化を図ることも重要です。事業の成長に伴い変化する課題やニーズに対して、柔軟な対応が可能な関係性を維持することで、より価値の高いパートナーシップを構築することができます。
結論:戦略的な税理士選定の重要性
スタートアップにとって、どんな税理士と提携するかは、非常に重要な経営判断です。
本記事で示した選定プロセスや確認ポイントを参考に、自社の特性と成長戦略に合致した税理士パートナーを見出すことで、持続的な成長への確かな一歩を踏み出すことができるでしょう。
グローブ税理士事務所はプレシードからアーリーステージまでのスタートアップ支援に特化しております。ご興味のあるスタートアップの方はぜひお問い合わせください。